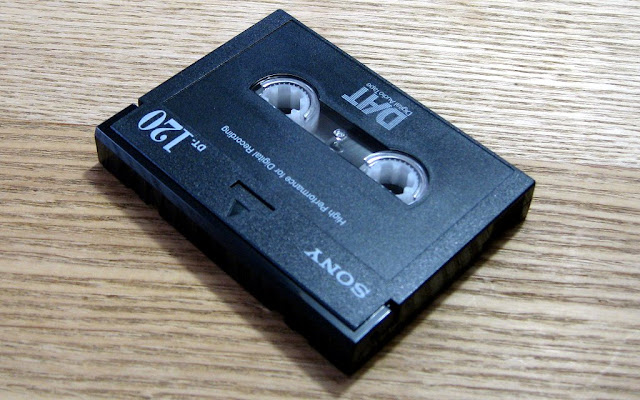仕事にも趣味にもパソコンとの付き合いは相当長くなりました。パソコンではなく、まだマイコンと呼ばれていた時代、8ビットのZ80 CPUが全盛だった頃からです。一部のマニアがパソコンの可能性に挑戦しながら、試行錯誤を重ねていました。まだインターネットが普及する前で、毎回モデムで電話回線につなぎ、料金を気にしながらパソコン通信に熱中したものです。1989年に東芝がDynaBookを発売した頃から、一部のマニアのものだったパソコンが一般の人にも普及し始め、その後ビジネスマンや学生が当たり前のようにノートパソコンを使いこなす時代がやってきました。
物置で見つけたThinkPad生誕10周年の記念品
物置を整理していたら奥の方からこんなものが出てきました。だいぶ前にノートパソコンを買った時におまけでもらったものだと思います。外箱にはThinkPad 10周年記念701C(模型)と書かれています。
 |
| おまけでもらったThinkPad 701Cの模型 |
ノートパソコン設計の際に、運び易さを優先してできるだけ小さくしようとすると、問題になるのがディスプレイとキーボードの大きさです。このThinkPad 701Cは、ディスプレイを閉じる時にキーボードが2分割されて小さくなり、筐体に収まるという画期的な機構を持っていました。その動きを再現したプラモデルです。
 |
| 組み立て前の701Cの模型がそのまま入っていた |
1992年に登場したThinkPadは今年で25周年
今年はThinkPad登場後25周年の記念の年だそうです。すると10周年記念の模型をもらったのは2002年頃のはずです。その頃手に入れたパソコンを思い返してみると、2001年の終わりにThinkPad X22を購入していました。その時のおまけがこの模型だったようです。
少し前にWindows XPのサポートが切れ、趣味や仕事で使うパソコンを一新しましたが、その前まではノートパソコンを購入するときは必ずThinkPadを選んでいました。黒一色の筐体と、しっかりとしたキーボードタッチが、他のノートパソコンにはない魅力でした。現在、手元に残っているThinkPadは3台あります。この当時はパソコン中核部品の性能向上が著しく、1〜2年で性能が倍以上なんてこともざらでした。さらにOSのバージョンが上がる度に必要スペックが上がるため、2〜3年に一度の頻度でパソコンを購入していたような気がします。今では信じられないような時代でした。当時のパソコン事業が儲かったのも頷けますね。
 |
| 現有している三台のThinkPad |
どれも十数年の年月が経った古いパソコンですが、実はすべて完動品です。OSはWindows XPまでアップグレードして使い続けてきました。Windows XPのサポートが切れた2014年以降はネットに接続せず、一部のアプリケーションのみを動かす専用機として現役で使われています。
 |
| 三台ともXPで今でもちゃんと動く |
ThinkPadが登場する一年前の1991年に発売されたPS/55 noteを入手したことが、その後のThinkPadとの長い付き合いの始まりでした。同じ年に発売されたWindows 3.1の喧騒の中でも、当時はまだまだDOSがパソコンOSの主流の頃です。ノートパソコンでWindowsを動かせるスペックのものはまだ出ていない時期で、PS/55 noteはDOSを快適に動かせるスペックを持つノートパソコンとして生まれてきました。メインメモリー2MB、HDD容量40MBという、今から思えば桁違いの低スペックですが、作りの堅牢さやデザインの良さからすっかりファンになってしまいました。その後次々に発表されるThinkPadの元祖にふさわしい作りだったと記憶しています。故障して動かなくなったため廃棄してしまったのが悔やまれます。保存しておけばよかった〜
XPで動くアプリ専用機として未だ現役のThinkPad
サポートのないWindows XPマシンをネットに接続して使用するのは危険なため、過去にインストールしたソフトのみを動かす専用機として、ネットから切り離して使用しています。Windows XPの時代が長く続いたため、このOSで稼働する優れたソフトが数多く存在しています。中でもefu氏作成のWaveGeneやWaveSpectraは、現在も多くの利用者がいる優れたソフトです。オーディオ信号を発生させるWaveGeneとオーディオ帯域の信号をFFT分析できるWaveSpectraは、オーディオ機器の調整に大変役立つソフトで、なくてはならないものになっています。10年以上も前の古いパソコンでも問題なく稼働しています。
 |
| オーディオ機器の調整に役立つWaveGeneやWaveSpectra専用機として現役のThinkPad X40 |
趣味のアマチュア無線では昔からRTTY(ラジオテレタイプ)などの無線データ通信がありました。以前は、一部マニアが中古のプロ用機器を手に入れて楽しんでいましたが、JE3HHT森氏が公開しているMMTTYやMMVARIを利用すると、パソコン一台で簡単に無線データ通信が楽しめるようになり、一気に広がりました。
 |
| パソコン一台で簡単に無線データ通信が始められるMMTTYやMMVARI |
これらのソフトはWindows XP登場以前に作られたこともあり、古いノートパソコンでも快適に動作します。十数年も前の古いThinkPadが未だ現役で活躍できるのも、これらの優れたソフトがあるおかげです。
でも今はThinkPadは買わない
日本の国内メーカーが次々にパソコン事業から撤退していますが、IBMも2005年に中国のLenovoにパソコン事業を売却しました。ThinkPadはLenovoの旗艦ブランドとして今でも発売されていますが、今ノートパソコンを買うとしたらThinkPadは選びません。理由はいくつかありますが、一番大きいのは「もうWindowsの世界からおさらばしたい」というものです。2013年に買い換えた仕事用のノートパソコンとして選んだのはMacBook Proでしたσ(^_^;) 生まれて初めてのMacです。
 |
| 仕事用に購入したMacBook Pro |
昔から抱いていたMacのイメージは「デザイナーなどの仕事用には向いているかもしれないが、システムエラーが多く、通常のビジネスではWindowsの方が使いやすい」というものでした。でも実際に使ってみると印象が一変です。想像力を掻き立てる豊富なアプリが揃っていることは以前のイメージどおりですが、安定していて作業中にフリーズするようなことも少なく、何よりも非常に美しいディスプレイのおかげで作業が格段にやりやすくなります。さすがRetina(網膜)と呼ばれる液晶ディスプレイです。システムのアップデートに対する方針にも大きな違いが見られます。Windowsのように勝手に更新を始めてしまうようなことはありません。今ではWindowsの世界にはもう戻れないと感じてしまうほどです。
ただし、世の中の考え方、特にお役所の世界ではWindowsが標準OSという位置付けは変わらないようです。仕事で使う電子申告用のアプリケーションは、Macの最新OSのサポートが遅く、Windowsパソコンがどうしても必要になりました。仕方なく価格優先で購入したのがLenovoのコンシューマー向けG50というものです。ThinkPadは価格で選択肢から外れました。
 |
| どうしてもWindowsが必要なアプリのために安いノートパソコンを購入 |
購入後にWindows 8から10へのアップデートが必要になり、その作業のためにほぼ半日が潰れてしまったのが懐かしい思い出です。その後もWindows君は、頼んでもいないシステム更新を勝手に始めて、何十分も作業をさせてくれないという失態を度々やらかしています。誰のパソコンだと思ってるんだと文句が出てきます。やっぱりWindowsにはもう戻れないですね。